むかし、三輪山のふもとに玄賓僧都(げんぴんそうず)というおぼうさんが住んでいました。りっぱなおぼうさんでありながら、そまつないおりで清らかにくらしていました。
このいおりに、ほとけさまにおそなえするしきみの木と水をもってかよってくる女がいました。ある秋のさびしい日のこと、その女が「夜も寒くなってきたので、ころもを一まいください」とたのみます。玄賓はたやすいことですと、ころもを与えました。女がよろこび帰ろうとするので、どこに住んでいるのかと尋ねると、「二本の杉を目じるしにおいでください」と言いのこしてすがたをけしました。
僧都は、里にすむ男から三輪のご神木にかかるころもがあると知らされ、二本の杉のもとへ行ってみると、そのころもが杉の枝にかかっていました。やがて女すがたにえぼしとかりぎぬをまとった大物主さまがあらわれ、三輪の神と活玉依姫(いくたまよりひめ)のものがたりをとき聞かせて、天の岩戸のかぐらをまいました。そして「おもえば伊勢の天照大神(あまてらすおおみかみ)と三輪の大物主の神がもともとひとつなのはいまさら言うまでもないたしかなことだ」と言って夜明けとともにきえていきました。
能「三輪」に描かれる物語です。能「三輪」は1465年、八代将軍足利義政が後小松上皇のもとに参上した際に初演され、大きな人気を得ました。三輪神道の教えを色濃く反映した格式の高い作品で、一説に世阿弥作とされています。
前半の玄賓僧都が衣を施す場面では、仏教の教えである「三輪清浄(さんりんしょうじょう)の布施」すなわち、施す者、受け取る者、布施の品物の三者にとらわれの心がなく清らかであることを暗示します。後半には、天照大神の姿をした大物主大神が現れ、三輪のおだまき伝説を語り、天の岩戸神楽を舞います。そして大物主大神は「思へば伊勢と三輪の神、一体分身の御事、今更何と磐座や」と、三輪と伊勢の神がもともとひとつであるという三輪神道の奥義を語って消えていきます。
大神神社では春の大神祭(三輪れんぞ)の後宴能で狂言「福の神」とともに上演されるのが吉例となっています。この伝統を通して、三輪の神とその信仰の深さを今に伝えているのです。

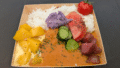
コメント