むかし、活玉依姫(いくたまよりひめ)という美しいむすめのもとに、夜な夜なかよってくる男がありました。たいそううるわしく、名もある方と見うけられましたが、いつも夜になるとむすめのところにやってきて夜が明ける前に帰ってしまうので、明るいところでそのすがたをたしかめることはありませんでした。ほどなくしてむすめはみごもりました。
親はその男のことをあやしんでむすめにたずねましたが、むすめも分からぬままです。そこで「その方がお帰りのとき、ゆかのまわりに赤い土をまき、麻の糸を通した針をそのころもにさしておきなさい。その糸をつたっていけばおすまいがわかるでしょう」とおしえました。
むすめがそのとおりにしてみると、赤くそまった糸が戸のかぎあなを通って長く長くのび、手元のおだまきには糸が三勾(みわ=三巻き)だけのこっていました。糸をたどっていくと三輪山の神のおやしろまでつづいていましたので、その方は三輪の大物主さまで、むすめがみごもったのは神の子であることがわかりました。
三勾の糸がのこっていたので、ここを三輪となづけました。
この活玉依姫が産んだ大物主命の子が大田田根子(おおたたねこ)で、崇神天皇により三輪に招かれて三輪山の祭祀を任されたとされます。大田田根子を祖として三輪氏が起こり、その後の大神神社の祭祀を引き継いでいきます。大田田根子は若宮さまとして馬場の大直禰子神社(おおたたねこじんじゃ)に祀られ、その石段の傍らには「おだまき杉」の大きな株が残っています。
この物語は、「古事記」に記された三輪の「おだまき伝説」として知られます。これを原型とする伝説は各地に伝わり、北は北海道から南は沖縄与那国島まで全国に残ります。
また、「おだまき」と「赤い糸」は、後世の物語や舞台芸術に大きな影響を与えました。特に人形浄瑠璃や歌舞伎の人気演目「妹背山婦女庭訓」では、ヒロインの三輪杉酒屋娘お三輪が手にする紅白のおだまきが、物語の運命を象徴する重要な小道具として用いられています。

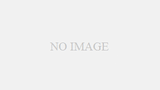
コメント